目次
「血液型で性格が分かる」という話、聞いたことがありますか? 占いのようで信じるかどうかは人それぞれですが、保育士として日々多くの子どもたちと関わっていると、血液型の違いから“なんとなく感じる傾向”があることも確かです。
この記事では、わたし自身が血液型に興味を持ったきっかけから、子どもたちとの関わりの中で見えてきた「液血型と性格の関係」や「保育・子育てへの活かし方」までを丁寧にご紹介しますね。
血液型に興味を持ったきっかけ――大学時代の不思議な体験
血液型に興味を持つようになったのは、大学生のときのこと。 女友達4人で旅行に行った際、偶然にもA型・B型・AB型・O型が一人ずつそろっていました。
そのとき、友人のひとりが「血液型人生論」という本を持ってきていて、ページをめくると面白いテストが載っていました。 「この中で、あなたが好感を持つ人を選んでみて」というもので、8人のアイドルの写真が並んでいました。 何気なくみんなで選んでみたところ――結果にびっくり!
なんと、4人それぞれ、自分の血液型ごとに好意を持つ人の傾向が違っていたのです。 ひとりだけなら偶然かもしれませんが、4人全員が一致したことで、「血液型って、もしかしたら性格や感覚に影響しているのかも?」と感じました。
それ以来、私は機会があるごとに血液型と性格の関係について調べるようになりました。 そして、保育士になり、多くの子どもたちと出会う中で、改めて血液型の不思議を感じるようになったのです。

子どもたちと接して分かる「血液型ごとの傾向」
もちろん、性格は環境や育ち方によっても変わります。 けれども、血液型によって“初めて出会ったときの反応”や“集団の中での動き方”に、少しずつ違いが見えることもあります。 以下は、わたしが長年の保育現場で感じた印象をもとにしたものです。
A型の子――まじめで丁寧、でも繊細な心を持つ
A型の子は、周囲をよく見て行動する傾向があります。 おもちゃを並べるときもきちんと順番を気にしたり、ルールを守ることを大切にしたりします。
一方で、叱られるととても落ち込んでしまう一面も。 保育士としては、「きちんとできたね」と小さなことでも褒めることで安心感を与えるのがポイントです。

B型の子――好奇心旺盛で自由!想像力が豊か
B型の子は、自由でマイペース。 新しい遊びや発見を楽しむ天才です。 ただし、集団生活では自分のペースを崩すことが苦手なため、周囲との衝突が起こることも。
そんなときは「あなたのアイデアすてきね」と認めたうえで、「お友だちと一緒にやってみようか」と誘うとスムーズです。

O型の子――おおらかで人懐っこい人気者
O型の子は、笑顔が多く、誰とでもすぐに仲良くなれるタイプ。 お友だちの面倒をよく見たり、小さい子を助けたりする姿もよく見られます。
ただし、意外と負けず嫌いな面もあり、競争遊びでは熱くなりがちです。 「勝ってもうれしい、負けても楽しい」という雰囲気づくりが大切です。
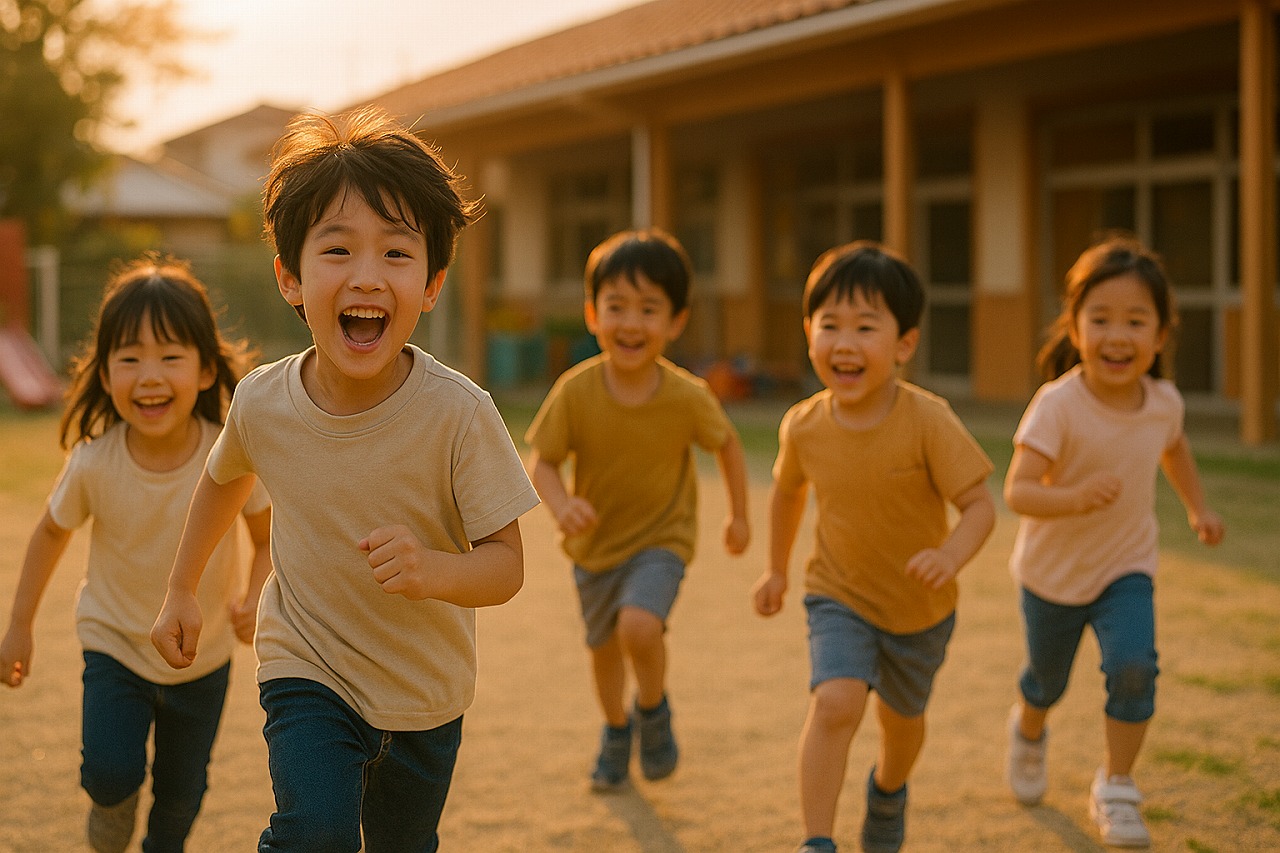
AB型の子――個性的で観察力が鋭い小さな研究者
AB型の子は、独自の世界観を持っていて、発想が豊か。 少し距離を置いて全体を観察するようなところがあります。
工作や絵を描くのが好きな子が多く、集中力も高め。 ただ、気分の波があるため、無理に合わせさせず「今はどうしたい?」と寄り添う対応が効果的です。

血液型から見る「保育のヒント」
血液型の話は、あくまで一つの“傾向”として捉えるのが大切です。
科学的に完全に証明されているわけではありませんが、保育士としては、子どもたちの性格を理解する「きっかけ」になります。
1. 声かけのトーンを工夫する
- A型の子には「丁寧な言葉」で安心を。
- B型の子には「自由さを認める言葉」でやる気を。
- O型の子には「頼りにしているよ」とリーダー意識を。
- AB型の子には「自分の考えを大事にしてね」と尊重を。
こうした声かけの違いが、子どもとの信頼関係を深める小さなカギになります。

2. 相性を理解してトラブルを減らす
血液型を意識していると、「あの子とこの子、合うかも」「少し距離を取った方が安心かも」という感覚が見えてくることも。
もちろん血液型だけで決めつけるのはNGですが、性格の傾向を知っておくことで、衝突を和らげたり、グループ分けの参考にしたりできます。
たとえば――
- A型とO型のペアは、バランスが良く安心感がある。
- B型とAB型のペアは、発想が広がる創造的な活動にぴったり。
- A型同士は丁寧すぎて慎重になりすぎることも。
- B型とO型はお互いマイペースで自由すぎることも。
相性を「理解」してサポートすれば、保育の現場でも子どもたちの成長をよりスムーズに支えられます。
家庭でもできる!血液型から見る子育てヒント
血液型の傾向は、家庭での子育てにも活かせます。 兄弟姉妹で性格がまったく違う場合、「血液型の違い」が背景にあることも。 ちょっと意識してみると、子どもの気持ちを理解しやすくなります。
A型の子どもには「安心できるルール」を
きっちりした性格のA型は、予定が変わると不安になることも。 「今日は予定が変わったけど、明日はいつも通りだよ」と伝えてあげるだけで落ち着きます。
B型の子どもには「選ぶ自由」を
「今日はどっちの服を着る?」「どの遊びをしたい?」と選択肢を与えることで、自分で考える力が育ちます。
O型の子どもには「頼る役割」を
「お手伝いしてくれる?」「お兄ちゃん頼もしいね」と声をかけると、嬉しそうに張り切ります。
AB型の子どもには「考える時間」を
すぐに答えを求めず、「どう思う?」と聞いて考えさせると、想像以上の答えが返ってくることもあります。

血液型は「ラベル」ではなく「理解のヒント」
血液型で人を決めつけてしまうのはよくありません。 けれども、「この子は慎重だから」「この子は自由で発想豊かだから」と、性格を理解するきっかけとして活かすことは、子育てにも保育にも役立ちます。
子どもたちは、血液型にかかわらず一人ひとり違う個性を持っています。 血液型の傾向を知っておくことで、より丁寧に寄り添える―― そんな“やさしい視点”として、取り入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ
血液型と性格・相性の関係は、科学的に明確ではないものの、保育士として現場で感じる小さな違いがあります。
A型の慎重さ、B型の自由さ、O型の包容力、AB型の独自性。 それぞれの個性を理解し、認め、活かしていくことが、保育にも子育てにもつながります。
血液型は「人を分けるためのもの」ではなく、「違いを楽しみ、支え合うためのヒント」。 子どもたちの“その子らしさ”を見つめるために、ひとつの参考として取り入れてみてくださいね。
・・・今日も一日ちはるびより
関連リンク
子どもの個性を伸ばす声かけのコツ
兄弟で性格が違うのはなぜ?血液型と環境の影響
保育士が見た「4つの性格タイプ」子どもとの向き合い方



